こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
ふるさと納税を行なっている人も増えていますが、多額の返礼品を受け取った場合には確定申告が必要となります。
その際の返礼品の価値について「自治体の調達価格によって算定すべき」という判決が2025年5月に確定しました。
今回は、ふるさと納税の返礼品と税金の関係について解説します。
ふるさと納税の返礼品は一時所得になる
まず、ふるさと納税の確定申告についてです。
ふるさと納税で受け取る返礼品は「一時所得」として確定申告が必要になるケースがあります。
返礼品は「寄付の対価ではない経済的な利益」として整理されており、一時所得に区分されます。
一時所得は、特別な控除額が設けられていて、
(総収入金額 − 必要経費 − 特別控除50万円) × 1/2 = 課税される所得
という計算式で求められます。
この「総収入金額」は返礼品の評価額ということになります。(この論点については後で解説します)
まずは、年間の返礼品の合計金額が50万円を超えたら、確定申告が必要になる点を知っておいて下さい。
また、ふるさと納税以外にも保険の解約返戻金や競馬などの利益も合算することになるので、他の収入がある場合にも注意が必要です。
裁判で示された返礼品の価値とは?
今回の裁判で争点となったのが、返礼品の「価値」をどう評価するかでした。
納税者は「小売価格の最安値」を主張しましたが、税務署は「自治体が返礼品を調達するために支出した金額(調達価格)」で評価すべきだと主張しました。
この「調達価格」が返礼品の価値として認められるのかどうかは、過去の国税不服審判所の裁決でも判断が示されています。(国税不服審判所名古屋支部令和4年3月1日裁決)
この裁決では「地方公共団体が返礼品の調達に要した費用が寄附者における返礼品の受領による経済的利益を受けた時の客観的交換価値」と判断しています。
地方公共団体は、返礼品を選定し調達するにあたり、予算計画や市場調査、事業者との交渉などを行っています。
その調達価格は、地方公共団体と事業者との間で、特別な事情なく決定されるものであり、客観的な価値を反映していると考えられるからと裁決で示されています。
そして、今回の最高裁まで争われた裁判でも、この国税不服審判所の判断と同様に、税務署が主張する「自治体の調達価格」での評価が妥当とされました。
また、「納税者が自治体に問い合わせて調達価格を確認する手間は、税務申告における当然の負担である」とまで言及されています。
実際に確定申告はどう対応すべきなのか?
今回の裁判では調達価格に基づいて申告すべきとされましたが、現時点とはふるさと納税のルールが変わっているため、現在には直接当てはまらないと考えています。
この裁判で争った事例は2017,2018年の申告についてですが、総務省は2019年6月、「寄付金額に対する返礼品の金額の割合は3割以下」と明確に定めました。
この基準に違反するとふるさと納税の対象から外されるため、現実的にふるさと納税の対象となっている自治体は寄付額の30%が返礼品の調達価格の上限と考えられます。
そのため、返礼品の評価額が50万円を超えるのは約166万円の寄付額ということになります。
なお、税額控除の上限額が166万円となるのは給与収入4000万円を超えるような方になるので、多くの方にとっては無関係の話かなと思います。
まとめ
今回はふるさと納税の返礼品の評価額について解説しましたが、現行ルールから考えると寄付額の30%を返礼品の評価額として申告すれば問題になることはないと思います。
また、ふるさと納税の返礼品だけで確定申告の対象となるのは多額の寄付を行った人に限られるので、多くの方にとっては無関係だと思っていて問題ないでしょう。
関連記事
参考 ふるさと納税の仕組みと歴史について〜問題点も紹介します〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ
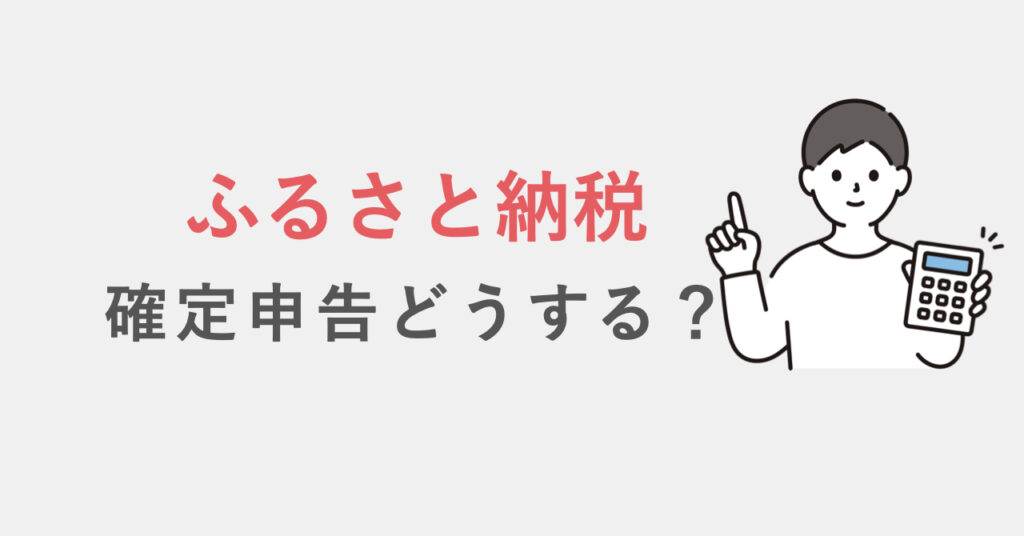


コメントを残す