こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
11月のタイミングで、4月に遡って非課税通勤費の改正が発表されました。
個人的には「来年1月からでいいじゃない」というのが本音ですし、バックオフィスに関わる人も同じ意見の人が多いんじゃないでしょうか。
改正の内容を紹介した上で、実務的にどう対応することになるのかを考えてみました。
改正の内容
2025年4月以降の非課税通勤費が改正されます。
改正の背景は物価高です。ガソリン代の高騰などから労働者の負担も増加しているということで今回の改正となりました。
なお、この制度は車通勤などが対象となるため、電車通勤の人には関係ありません。
片道10km未満であれば変更はありませんが、10キロ以上で距離に応じて増額されます。
| 片道の通勤距離 | 1ヶ月の限度額 (改正前との比較) |
|---|---|
| 2キロ以上10キロ未満 | 変更なし |
| 15キロ未満 | 7,300円(200円増) |
| 25キロ未満 | 13,500円(600円増) |
| 35キロ未満 | 19,700円(1,000円増) |
| 45キロ未満 | 25,900円(1,500円増) |
| 55キロ未満 | 32,300円(4,300円増) |
| 55キロ以上 | 38,700円(7,100円増) |
しかし、問題はこの改正が2025年4月に遡って実施されるということです。
では、実務的にどのような対応が必要なのか考えてみましょう。
年末調整で対応できるケースとできないケース
報道などでは「年末調整で対応する」と言われていますが、必ずしも年末調整では対応しきれないケースも考えられます。
まぁ、政治家や財務省の官僚が細かな実務を知っているとは思いませんが、それにしても現場の実務を無視しすぎているなと思いますね。
まずは一般的な年末調整で対応するケースを考えてみましょう。
年末調整でどう対応するか
12月時点で会社に在職している人は年末調整の対象となります。
そのため、多くの人は年末調整で対応されることとなります。
対応が必要となるのは
・自動車通勤などで通勤費が支給されている
・通勤費が改正前の非課税限度額を超えている
というケースです。
ただ、年末調整の処理をする人は実際にどう対応するかが問題になります。
多くの会社はシステムで対応しており、給与計算の結果が年末調整システムと連携する仕組みになっていると思います。
そこで問題となるのは、4月以降の給与計算は確定しており、課税支給額や源泉徴収税額を遡って変更することはできない点です。
給与明細は従業員に渡しているし、源泉所得税の納付も済ませているので、今更変更できないという訳です。
年末調整の実施までにバージョンアップが実施されるシステムであれば差額を自動計算できる可能性はありますが、スケジュール的にかなり厳しいでしょう。
ほとんどの年末調整システムは既に今年度版がリリースされていますし。
そのため、従業員別に影響額を計算して、個別で対応する必要が生じる可能性があります。
もうミスが起きる気しかしませんね。
頭の切れる財務省の官僚なら何てことはないのかもしれませんが、私みたいな凡人には気が重いです。
具体的な流れとしては
①対象となる従業員の影響額を計算する
②給与計算から年末調整システムへ給与額を連携する
③源泉徴収簿の12月分の金額に①を反映させる
となるでしょう。
例えば通勤距離が20キロで通勤手当が毎月14,000円だったとします。
その場合、非課税となる金額は毎月600円増加するため、12月分までで5,400円課税支給額が少なくなります。
(12月の給与計算も旧限度額で計算されているとした場合です)
そのため、12月分の源泉徴収簿に△5,400円と追加で入力して対応することになるでしょう。
源泉徴収簿の総支給金額などの欄は2行あるので、給与連携後に空欄となっている行に追記すれば大丈夫です。
退職者は年末調整で対応できない
当然の話ですが、4月以降に退職した従業員は年末調整は実施できません。
退職しているので当然ですよね。
そのため、退職者のうち改正の影響を受ける人には再計算した源泉徴収票を発行することになります。
マジ面倒ですよね。
計算方法としては年末調整で対応するケースと同じですが、計算期間が4月から退職までの期間になる点が異なります。
例えば通勤距離が20キロで通勤手当が毎月14,000円だったケースで、10月退職だとします。
その場合、非課税となる金額は毎月600円増加するため、10月分までで4,200円課税支給額が少なくなります。
源泉徴収簿にも同様に10月の欄に△4,200円と追記し、新たしい源泉徴収票を発行します。
ただ、退職後に転居していたり連絡先が変わっている場合は新しい源泉徴収票を渡せないケースも出るでしょうね…
まとめ
従業員としては非課税額が増えるため、車通勤の従業員にとってはメリットがあると思います。
ただ、現実的にこの実務の対応をさせられる企業のバックオフィスや会計事務所からすれば「この労力はタダじゃねーよ」という気持ちですよね。
今年は基礎控除の魔改造や特定親族特別控除なども年の途中で正式決定し大きく混乱しました。
実際に年の途中で亡くなった方の準確定申告などでは更正の請求が必要になるなど、実務的な手間を無視したような改正でしたしね。
昨年の定額減税もそうですが、最近は実務的な影響を無視して「減税してやるんだからいいだろう」みたいな姿勢を感じてしまいます。私だけでしょうか。
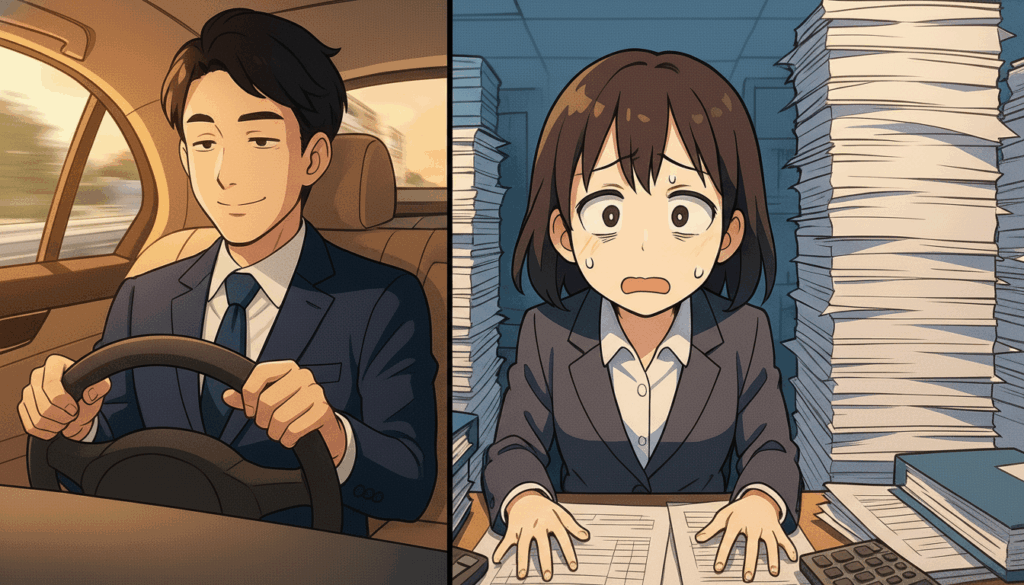
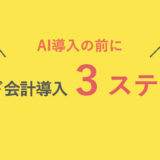

コメントを残す