こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
ここ最近は「AIを使った経理の効率化」といった情報を見掛けることが増えています。
もちろん、AIを活用することで効率化できることは沢山ありますが、経理業務の土台となる部分を固めなければAIを使っても意味がないんですよね。
近年では普及率も上がっていますが、経理効率化の基本はクラウド会計の導入です。
しかし、「クラウド会計って何から始めればいいの?」「本当にうちのビジネスに合っているの?」といった声もまだまだ耳にします。
今回は、クラウド会計の基本的な流れから、導入のメリット・デメリット、そして「AIに頼るべきか」という問いまで、税理士の視点から分かりやすく解説していきます。
Contents
クラウド会計の主な特徴
クラウド会計を導入すると、日々の経理業務は劇的に変化します。その中心となるのが、データの自動連携と仕訳の自動生成です。
1.ネットバンクやクレジットカードとの連携
インターネットバンキングや法人カードの利用明細をAPI連携でクラウド会計ソフトに自動で取り込みます。
デジタルデータで連携するので、数字の入力ミスなどが発生することはありません。
手入力に比べると早さも正確性も段違いです。
2.取引情報の自動仕訳
取り込まれた取引情報に対し、事前に設定したルールに基づいて勘定科目を呼び出すことができます。
例えば、「中部電力」であれば「水道光熱費」、「JR東海」であれば「旅費交通費」といったイメージです。
また、、多くのクラウド会計ソフトは学習機能を持っており、ルール登録がなくても過去の仕訳データや一般的な取引パターンから勘定科目を推測してくれます。
特に「タクシー」や「ホテル」のような分かりやすいキーワードはほぼ間違いなく「旅費交通費」で表示されますし、ルールが存在しない取引でもある程度の精度で勘定科目が提案されます。
3.周辺システムとの連携
請求書発行システムや給与計算システムなど、他の業務システムとも連携が可能です。
これにより、仕訳の自動生成だけでなく、売掛金の入金消し込み管理や給与関連の仕訳も自動化され、経理業務全体の効率が向上します。
クラウド会計に向く業種と向かない業種
クラウド会計は非常に便利なツールですが、効率化できる度合いは業種などによって異なります。
ご自身の業種や経理の状況などを踏まえて、確認してみましょう。
クラウド会計で効率化しやすい業種
主にデジタルデータでの取引が多い業種は、クラウド会計の恩恵を最大限に受けられます。
①サービス業
在庫管理が不要なケースも多く、資金の流れも比較的シンプルなので、大部分をクラウド会計で管理することが可能になります。
②飲食業
POSレジの導入などにより、売上データを連携することができ、かなり効率化できます。
このように、売上データ、入出金データなどクラウド会計と連携できる情報で会計データの大部分を作成できる業種であれば効率化の恩恵を大きく受けることができます。
クラウド会計で効率化しにくい業種・取引
一方で、アナログな情報が多い取引や、特殊な管理が必要な業種では、クラウド会計だけでは効率化が難しい場合があります。
次のようなケースではクラウド会計のみでは対応が難しいため、効率化を感じにくい原因になります。
①紙の手形、小切手
これらはそもそもアナログ情報であるため、システム連携は不可能です。
デジタル化されていない情報は、手入力などにより対応する必要があるので、クラウド会計のメリットを生かしきれません。
②でんさい(電子記録債権)
電子データではありますが、現状のクラウド会計ソフトとの直接連携は難しいケースが多いです。
③現金取引
小口現金で経費支払いを行っているような場合には、データ連携しないため手入力などでの対応が必要になります。
ただし、飲食店のようにPOSレジで現金売上も管理している場合はデータとして連携できるため問題ありません。
(もちろん、釣銭のミスなど別のリスクはありますが)
④在庫管理
クラウド会計ソフトが自動で棚卸しをしてくれるわけではありません。
在庫の入出庫管理や評価は、別途専門のシステムや手作業が必要です。
⑤工事台帳
建設業などで用いられる工事台帳は、会計処理の前段階である工事管理の領域です。
会計ソフトが直接管理するものではなく、連携には工夫が必要です。
小規模の建設業であればメモタグ機能で対応できるケースもありますが、限界はあります。
上記のように、建設業や製造業などは工事台帳の作成や原価計算などクラウド会計で直接対応し切れない経理業務が存在します。
また、手形・小切手での決済のようにアナログな取引が多いと、デジタル化の恩恵を受けにくくなります。
ただし、これらの業種でも、一部の業務をデジタル化したり連携可能なシステムを導入したりすることで、効率化の余地は十分にあります。
クラウド会計の導入の3ステップ
クラウド会計のメリットを最大限に享受するためには、導入前の準備が非常に重要です。
ここでは、スムーズな移行と効率的な運用を実現するための具体的なステップをご紹介します。
1.銀行口座は全てネットバンキングに移行する
クラウド会計の最大の利点は、銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取り込める点にあります。
この自動連携をフル活用するためには、事業で使用する全ての銀行口座をネットバンキングに切り替えることが不可欠です。
これにより、通帳記帳や手入力の手間から解放されます。
2.現金取引を極力減らす
現金での取引は、デジタルデータとして自動連携することができません。
そのため、現金での入出金が多いと、結局手入力やレシートのスキャンといった作業が発生し、クラウド会計導入のメリットが半減してしまいます。
可能な限りキャッシュレス決済に移行し、現金取引を最小限に抑えましょう。
3.給与計算や請求書発行も連携可能なシステムへ移行する
給与計算ソフトや請求書発行システムも、クラウド会計ソフトと連携できるものを選ぶことで、仕訳の自動生成や入金消し込みといった業務がさらに効率化されます。
連携しないシステムを使っていると、データの二重入力や手作業での連携が必要になり、効率が悪くなります。
基本的には会計ソフトの系列の請求書機能や給与計算機能を使えば問題ないですが、別システムを利用する場合でも会計ソフトとの連携の有無は確認しておくべきでしょう。
これらの準備を事前に行うことで、クラウド会計導入後の運用が格段にスムーズになり、真の業務効率化を実現することができます。
AIに頼るべきか?~本質的な効率化のために~
近年、「AIが経理業務を自動化してくれる」という話もよく耳にします。
通帳などをAIでデータ化するサービスも登場していますが、私はこれを邪道だと考えています。
紙の通帳をスキャンしてAIで読み取るというプロセスは、デジタル化されていない情報を無理やりデジタルに変換する無駄な作業です。
ネットバンキングを利用すれば、最初からデジタルデータとして取引履歴を取得できます。
無駄な作業は、そもそもやらない。
これが、業務効率化の鉄則です。
AIはあくまで補助ツールであり、業務プロセスそのものを見直し、無駄をなくすことが最も重要です。
まとめ
クラウド会計は、日々の経理業務を効率化し、事業の成長を加速させる強力なツールです。
しかし、その導入にあたっては、自社のビジネスモデルや取引形態を深く理解し、最適なシステム連携と業務プロセスの見直しを行うことが不可欠です。
「AIを入れたら解決」という安易な考えではなく、本質的な効率化を目指し、デジタル化できる部分は徹底的にデジタル化する。
この視点を持つことが、クラウド会計を成功させる鍵となるでしょう。
ご自身のビジネスに合ったクラウド会計の導入や、さらなる業務効率化についてご不明な点があれば、ぜひ専門家にご相談ください。
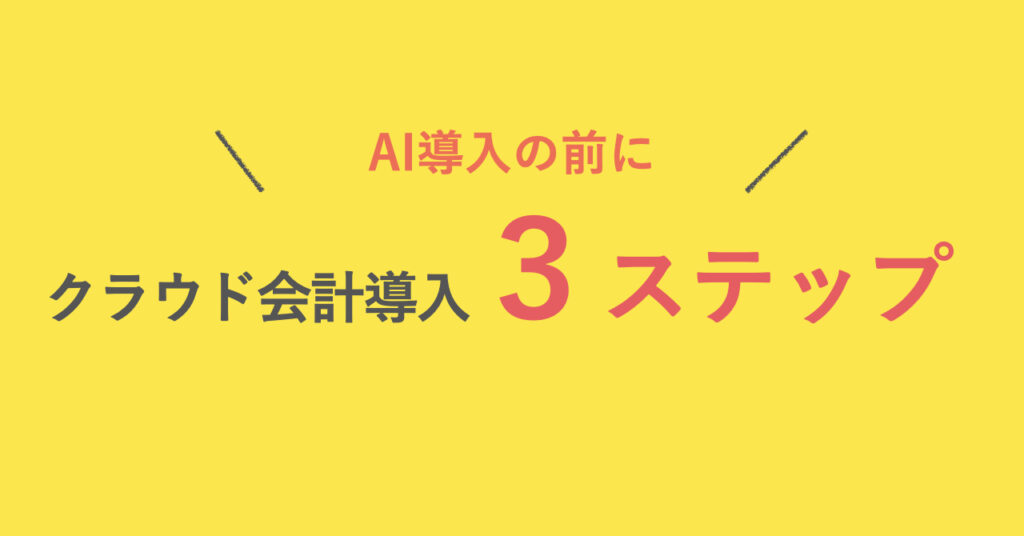
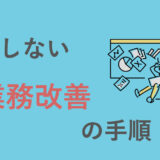

コメントを残す